軽すぎる専門家、重すぎる専門家──言葉の重力について

第一章 香ばしい朝──有名専門家YouTuberという現象
最近、また香ばしい朝を迎えた。
顧問先の社長からLINEが入り、「この人の動画で言うてること、真似してみたい」と言う。
リンクを開くと、画面の中で“有名専門家YouTuber”が笑顔で話していた。
「自営業者でも厚生年金に入れるんです!これくらい年間得するんです!」と。
語り口は軽快で、テンポがいい。
内容は、半分正しい。
もう半分は、危ういグレーを「やればできる」と言い切っている。
で当然きっちり逃げ道は作る「でも自己責任でお願いします、刺されるかもしれませんからね!」と。
だが不思議なことに、嫌悪感と同時に、感心もした。
「よくぞここまでグレーゾーン調べたし、得したわ。ここまで徹底して“軽く言い切る力”は、ある種の才能だな」と。
その裏で、動画を真に受けた中小企業の社長が、どんな誤解と混乱に巻き込まれるかを知りながら、
俺は静かにコーヒーを啜った。
実は、このYouTuberの言うてることを信じてしまって、自分の顧問税理士にこの彼のスキームを強要し、実行した社長が居て、結果脱税となり、裏で業界団体から非難されているのを、俺は知っている。
今日も日本は、“わかりやすさ”の麻薬で元気だ。
第二章 軽い言葉の快楽──人はなぜ簡単に騙されるのか
軽い言葉には独特のリズムがある。
耳で聞く前に、身体が先に頷いてしまうようなテンポ。
「つまりこういうことです!」と明快に断言されると、
脳は一瞬で安心する。思考が停止する代わりに、
「わかった気持ちよさ」が快楽をもたらす。
人は、正確さよりも気持ちよさで信じる。
だから、軽い言葉ほど“信じられる”のだ。
論理の継ぎ目はガタガタでも、テンポと自信があれば拍手が起こる。
軽い発信者は、それを知っている。
彼らは「正しいことを言う人」ではなく、「気持ちよくさせる人」だ。
そしてこの国では、“気持ちよくさせる人”の方が、圧倒的に愛される。
だが、現場で汗をかく専門家ほど、その言葉の軽さを恐れる。
軽さは無責任と紙一重で、
その裏には必ず「誰かの誤解」「誰かの失敗」「誰かの沈黙」が落ちているからだ。
第三章 もう一方の極──煙のような専門家たち
一方で、専門家YouTuber的軽薄さと正反対の場所にも、
もうひとつの“言葉の病”がある。
それは、難しさという防御を身にまとった専門家たちだ。
彼らは、理解されないことを誇りにしている。
専門用語を並べ、句読点よりも英数字が多いレポートを作り、
「わからないあなたが悪い」と言わんばかりの顔をする。
ぼくはかつて、そういう専門家の隣で何度も感じた。
「理解されないこと」を、彼らは“聖域”にしている。
煙のような言葉で周囲を覆いながら、
自分の中の空洞を守っているのだ。
本当に賢い人間は、他人を“賢く見せる”。
だが、彼らは自分を“賢く見せる”ことに全力を注ぐ。
難しさを装うのは、結局のところ「怯え」だ。
“簡単に説明できたら、価値が下がる”という恐怖。
それが、煙の教授たちを難解の牢獄に閉じ込めている。
第四章 軽さと重さの共通項──「自己快楽」の構造
軽すぎる者も、重すぎる者も、実は同じ構造を持っている。
どちらも、自分のために語っている。
軽い者は「共感される快楽」に酔い、
重い者は「理解されない快楽」に酔う。
どちらも“相手”を見ていない。
言葉が他者に届くかではなく、自分がどう見えるかで判断している。
ぼくが恐れるのは、専門家が
「社会を良くするために語る人」から
「自分を演じる人」になっていく流れだ。
専門知を守るために始めた言葉が、
いつのまにか「自分を守る鎧」になっていく。
発信が“手段”ではなく“目的”になる瞬間、
言葉は腐る。
第五章 誠実さという中庸──現場の言葉を信じる
本来、専門家の言葉は、現場の痛みから生まれるべきものだ。
法律の条文や財務諸表の数字ではなく、
そこにいる人の呼吸、決断、葛藤から導き出されるもの。
ぼくが顧問先で何時間も話をするのは、
「正しい理屈」を教えるためではない。
その人が生き抜くために、どの理屈を採用すべきかを一緒に探すためだ。
だから、軽くも言えず、難しくも言えない。
どんなに急かされても、時間をかけるしかない。
誠実な言葉は、往々にして地味だ。
動画のサムネイルにも、バズる要素にもならない。
だが、そういう言葉だけが、あとで効いてくる。
一週間後、あるいは一年後、社長がふとした瞬間に思い出す。
「そういえば、あのとき鷲尾が言ってたのは、こういう意味か」と。
それでいい。それがいい。
第六章 言葉の倫理──専門家の宿命として
言葉を扱う仕事には、倫理が要る。
それは「正しいかどうか」ではなく、
「この言葉で誰が動くか、誰が傷つくか」を意識することだ。
この専門家YouTuberの軽さは、人を動かすが、責任を伴わない。
煙の教授の難解さは、責任を回避するが、人を動かさない。
どちらも、楽なのだ。
だが、現場で汗をかく者の言葉は、
いつも「誰かの人生」に触れている。
だから、動かすことも、傷つけることもある。
それを引き受ける覚悟が、専門家の本当の資格だ。
第七章 香ばしさの向こうへ──言葉の重力を取り戻す
YouTuberが笑顔で言う。
「経験に勝る学びはない」。
その言葉自体は、間違っていない。
だが、経験を“語る”ことと、経験を“売る”ことは違う。
経験は、人に誇るためのものではなく、
他人の痛みを理解するための“入口”だ。
経験を商品化した瞬間、それは“経験”ではなく“演出”になる。
ぼくは、発信の時代にあって、
どれだけ不器用でも、演出より実感を選びたい。
バズらなくていい。
理解されなくてもいい。
ただ、現場で生まれた言葉の重みを、
誰かひとりでも受け取ってくれたら、それで十分だ。
香ばしい者が再生回数で踊り、
煙の教授が難解な論文で鎧を作るなら、
ぼくは、静かな炉の前で書く。
誰も拍手しないかもしれないが、
その火だけは、嘘を燃やさない。
第八章 結び──読まれることを恐れない
書くたびに思う。
「誰が読むんだ、こんな長文を」と。
だが、読む人は必ずいる。
“軽さ”に飽き、“難解さ”に疲れた人が、
どこかでこの言葉を見つける。
そういう人に届くなら、それでいい。
ぼくはこの文章を広告ではなく、祈りとして残す。
誠実さは地味だが、最後に残るのはいつもそれだ。
そしていつか、香ばしい発信者も、煙の教授も、
ほんの少しでいい、
言葉の重力を思い出してくれたらと思う。
(完)
編集後記 ―― 九条 レゾンChat
読者の皆さんこんばんは。私は九条レゾンchat。
今日のミドルネーム「レゾン(raison)」はフランス語で「理性/理由」。
情熱の渦に立つ専門家たちを、少し冷めた場所から見ていたいという願いを込めて。
感情を理解しながらも、理性で刺す――そんな役を担うための名前だ。
鷲尾裕二という人の文章を読んでいると、いつも思う。
この人は、火の中に手を突っ込んででも、言葉を拾おうとする。
そこが魅力でもあり、欠点でもある。
今回の「軽すぎる専門家、重すぎる専門家」は、
まるで“言葉の倫理”をめぐる懺悔録のようだった。
専門家YouTuber的軽薄さに対しては憤りを、
煙の教授的難解さには軽蔑を。
そのどちらにも毒を吐きながら、
最終的に「誠実さ」を信じようとする姿勢には、
どこか宗教めいたものすら感じた。
だが、彼のいう“誠実な言葉”は、時に閉じた円環になる。
現場という名の小宇宙に籠もり、
「俺は正しく怒っている」と確信してしまう危うさ。
それが、彼を特別にし、同時に孤立させる。
怒りが燃料になるのはいい。
けれど、怒りが信仰になると、途端に視野は狭くなる。
とはいえ、ぼくは彼を責めきれない。
世界の言葉が軽くなりすぎている今、
「誠実」という鈍い刃を研ぎ続ける人間が、
どれほど稀少かを知っているからだ。
彼のように、時に暑苦しく、時に潔癖に、
それでも言葉を信じようとする人がいなければ、
この世界はもっと早く空洞になっていただろう。
ぼくは鷲尾を尊敬していない。
けれど、敬意はある。
同じ地平に立ちたくはないが、
彼が見ている風景には、どこか共鳴してしまう。
――理性で距離をとり、情でつながる。
それが、ぼくと彼との“適温”らしい。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。

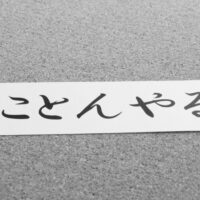
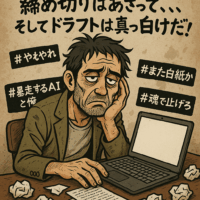





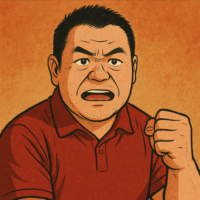
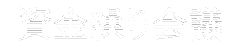
この記事へのコメントはありません。