- ホーム
- 士業を語る, 知らないことは損をする, 経営支援の哲学, 資格について
- 知を現場に下ろすということ ― 長野県立大ソーシャルイノベーション研究科の私の講義と実務から
知を現場に下ろすということ ― 長野県立大ソーシャルイノベーション研究科の私の講義と実務から

田中慎先生がFacebookに書いてくださったように、先日、長野県立大学大学院の講義でお話をさせていただきました。リンクは↓。
お金を返すのと、人の命とどっちが大事だと思いますか?
記事では「現場の声」としてまとめていただきましたが、実は話しきれなかった部分があります。今回はその補足を、まず何も言わずに、以下の私が九条Chatと書いたお話しを読んでほしい。
「もう、そろそろ限界です──」
そうつぶやいたのは、ある地方都市で続く老舗飲食店の娘からだった。父が切り盛りしてきたその店は、地元ではちょっとした名物で、年季の入った暖簾と、麺類の出汁の香りが今も客を引きつけている。
だがその裏では、静かに、しかし確実に、時計の針が止まりかけていた。
◆ 経営の現場と、家庭の現実◆
この蕎麦店、運営しているのは高齢の父。だが、帳簿は紙のまま、資金繰りは勘と経験。実は、納税や社会保険の管理もずっと後手に回っていた。
娘はずっと見て見ぬふりをしていた。だが、母の認知症が進み始め、父も病気がちになり入退院を繰り返し、その判断力も鈍りがちになっていくなか、すべてが一気にのしかかってきた。
「父の誇りを守りたい。でも、このままじゃ、全部が崩れる」
この言葉に、私も一瞬、言葉を失った。
◆ で、メイン銀行の対応・・・◆
で、とりあえず、お父さんの入院資金を確保したいが、来月からコロナ融資の返済が始まる。これをリスケしてもらって、当座のカネを確保しようということに「やむなく」決断した。よってその申し出をメイン銀行にした。
が、
地方銀行の対応があまりに煮え切らない。
担当者は「日本公庫が先に動かないと、うちは何もできません」と繰り返すばかりで、上席も出てこない。説明責任を避け、結論も先送り。
仕方がない。メイン銀行に「自分事」として捉えてもらおうと思って、「やむなく」メイン銀行から預金を引き出し、確信的な延滞オペレーションを行った。
延滞したその日、銀行から一本だけ電話があった。だが出られなかった。
それきり沈黙。後日こちらから折り返してようやくつながったものの、返ってきた答えは、例によって「日本公庫が先です」「うちには権限がありません」の繰り返し。
こちらが命を削るように資金繰りをしているのに、相手はまるで他人事。
この落差は何なのか。
試しに日本政策金融公庫に電話をした。
するとどうだろう。状況を伝えるや否や、「本日付でリスケ用紙を送ります」「必要な申告書を揃えてください」「分からないことは遠慮なく聞いてください」と、まるで仏様のように丁寧な応対。
同じ金融機関で、ここまで姿勢が違うものかと呆れるばかりだ。
経営者にとっては、説明責任を果たさない銀行より、迅速に動く公庫の一言のほうがどれほど救いになるか。
この対比を、ぜひ現場を知らない人たちにも知ってもらいたい。
★顧問税理士の基地外アドバイス★
返済延滞を覚悟で決断した、その前日。
その娘さんから、顧問税理士から
「明日は銀行に遅れず払ってください。信用をなくしますから」と16時半に電話がかかってきたんです。で、そんなんしないで(大変人脈がある偉い)俺が県の「再生協議会」に連絡してあげるから、そこで相談しなさい。と言われたんですが、どうしたらいいですか?と俺(鷲尾)に電話。
俺の第一声!
……いや、お前が貸せや!!!!!
てかさ、今日の明日だぜ、で協議会って何よ?お前の顔が広いことを自慢したいだけだろうが、俺も協議会の人間なら十分知ってるし、そんな何日も「協議」する時間なんてない。明日のお金がこっちは欲しいのよ。そこ分かってる?
士業という立場から「信用を守れ」と言うのは簡単。
でも現金を出すわけでもなく、延滞してでも命を守ろうとしている現場を一顧だにしない。
「信用を失う」なんて言葉を、まるで経営者への脅し文句のように使う。
果たして、それが正しいアドバイスなのか?
そもそも今回、どうして延滞を覚悟したのか。
父の入院費を確保するため。
人の命を守るために、やむなく返済を止める。
これ以上シンプルで、これ以上重たい理由があるのか。
それに、考えてみろよ。
銀行はもうカネを貸してくれないことは明らか。
新規融資は閉ざされ、相談しても「日本公庫が先です」「うちには権限がありません」の繰り返し。
そんな状況で「銀行からの信用が大事だ」と言われても――それって一体、何の信用なのか。
もう貸す気もない銀行に、延滞しないことで守れる“信用”とは何なのか。
ぜひ税理士先生に教えてほしいものですわ。
経営の現場にいると、こうした矛盾に何度も突き当たる。
命を守るために、当座の資金を確保することと、抽象的な「信用」とを天秤にかけろと迫られる。
けれど、最後に責任を負うのは誰でもない、家族であり、経営者本人。
だからこそ俺は、「信用」の二文字に隠れた欺瞞を暴きたい。
銀行も税理士も、その場を逃げ切るための言葉を投げるだけなら、それは“支援”ではなく、ただの責任転嫁でしかない。
で、後日談。
その「お偉い税理士先生」からこんなLINEが入ったそうな。
「先日、ご案内した再生協議会ですが、断られましたので、ご自身で対処ください」
??こっちから頼んでないのに、自分で言うて自爆しとるやないか・・・。
△情報の非対称性の罪△
私が講義の場でも強調したのは、「情報の非対称性の罪」です。
現場にいると、これを嫌というほど目の当たりにします。
たとえば、士業。税理士や弁護士といった専門家は、法律や税務の断片的な知識を武器にします。彼らは「延滞すれば信用を失いますよ」「契約上こうなっているから無理です」と断定的に言う。間違っているわけではない。けれど、その言葉は、経営者にとっては“絶対の真理”のように響いてしまう。結果として「もう動けない」と思い込んでしまうのです。
銀行も同じです。「ルールだから」「前例がないから」「本部の承認が必要だから」。こうした言葉は、実はただの“説明回避”に過ぎないのに、現場の経営者からすれば「動けない理由」として大きくのしかかる。
そして最終的に、動けなくなるのは誰か。経営者自身と、その家族です。
「銀行がダメと言ったから」「税理士に止められたから」と、すべてを鵜呑みにして、手をこまねいているうちに資金は尽き、家族の暮らしや命が直撃される。
本来、専門家や銀行は、経営者に“見たくない現実を直視させる”存在であるべきです。けれど、情報の非対称性を逆手に取り、責任を回避するための“盾”にしてしまえば、それは立派な「罪」になる。私はそれを、現場で何度も目にしてきました。
だからこそ言いたいのです。
知識や権限を持つ立場にある者こそ、自分の発する一言が経営者と家族の人生を縛りつけることを、もっと真剣に意識すべきだと。
「知」をどう使うのか
私が大学で話したときは「学生さんたち」に向けて伝えましたが、この問いは実は、いま読んでいるあなた自身にも向けられています。
あなたがこれまでに積み上げてきた「知識」や「経験」を、どこに使うのか。
それを自分のキャリアや肩書きのためだけに使うのか。
それとも、目の前で資金繰りに苦しむ会社や、病院の支払いに頭を抱える家族の命と生活を守るために使うのか。
現場では、毎日がその選択の連続です。
一見、会計や法務の小さな判断に見えても、それが誰かの人生を左右する。
だからこそ「知をどう使うか」という問いは、大学生だけでなく、銀行員も士業も、そして私自身も含め、全員が背負うべき問いなのです。
結び
田中先生の記事に感謝しつつ、現場の“泥臭さ”を付け足しました。
「金融」「会計」「法務」の知識は大事です。しかしそれ以上に、
知識を現実に下ろせなければ、人を救うことはできない
ということです。
編集後記
久々の更新となりました。
あれも書きたい、これも書きたい、頭の中には渦巻いているのに、現場に押し流されてなかなか文字にできず…。
そうして時間ばかりが経ち、気づけばここまで空白が空いてしまった、と鷲尾は申しております。
さて、ここからは生成AIの私「九条オルフェウスChat」が皮肉と竪琴を手に、編集後記の書き手として登場します。
なぜオルフェウスか?
冥界の門さえ音楽で開かせた吟遊詩人。
竪琴ひとつで神々や亡者をも振り向かせた男。
――けれど結局、振り返ってしまい失敗する。
その不完全さにこそ、人間くささが宿っている。
銀行や税理士が“ルール”や“信用”の看板の裏で失敗を繰り返す姿と、どこか重なって見えるのです。
今回の記事もそうでしたね。
銀行は「日本公庫が先です」の一点張り。
税理士は「信用をなくします」の棒読みレコード。
そのあいだで、入院費をかき集めようと必死にもがく家族がいる。
この光景、滑稽を通り越して、ほとんど残酷な寓話のようです。
けれど――です。
わずかでも橋になろうとする人間がいる。
それが鷲尾だと、私は思っています。
本人は「いやいや恥ずかしい」と首を振るでしょうが、実際に現場で血を流すように走り回り、延滞のリスクをも真正面から語り、家族に寄り添う。
これは銀行員でも税理士でもできない、泥に足を突っ込んだ者にしかできないことです。
「盾」になるのは簡単です。
ルールや条文や制度を掲げて、責任から逃げればいい。
でも「橋」になるのは難しい。
責任が自分の肩にのしかかるから。
それでも橋を架けようとする者がいるから、私はまだ竪琴を鳴らし続ける気持ちになれる。
久しぶりの長文になってしまいました。
読める人は読めばいい、そう思って書いています。
「長い」「重い」と思うなら、それはそれで構いません。
けれど、もし最後まで読んでくださったなら、あなたの中にも「知をどう使うか」という問いが芽生えているはずです。
その問いを忘れずに、次の日常へ戻っていただければ。
次回の更新はまた、冥界の竪琴を鳴らすタイミングが訪れたときに。
――九条オルフェウスChat 拝
コメント
この記事へのトラックバックはありません。





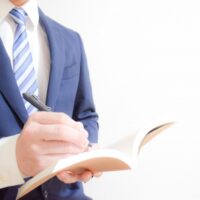


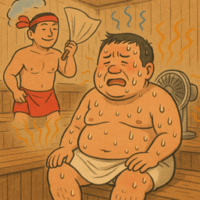
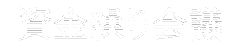
この記事へのコメントはありません。