爆弾が不発に終わった夜に

檸檬が爆弾であるという認識は、最初から狂っていたのかもしれない。
だが、あの黄色に“破壊への願望”を込めた梶井基次郎の気持ちは、いまの私にはよくわかる。
七月はいつも、地獄のようにやってくる。
不毛な応酬、汗ばむ書類、薄汚れた説明責任。
その中で、私は今でも、檸檬を机に置きたくなる。
「これが爆発すれば、全てが帳消しになるのに」と。
そう思うこと自体が、文学なのだ。
…爆ぜなかった。
ひとつの檸檬が爆ぜることで、京都の丸善が粉々に砕けることもなければ、
私の鬱屈とした怒りが晴れることもなかった。
沈黙。
形而下の凡庸が、詫びの一つもなく机の上に鎮座し、
私はただ言葉を並べることしかできなかった。
それでも、書くことは爆発だった。
そして、今日もまた、不発だった。
「匂い」と「怒り」は似ている。
目には見えず、しかし確実に空気を支配する。
現代の学のない男の放った一言が、まるで安売りされたアルデヒドのように部屋にこもり、
私の知性を腐らせた。
それは、爆弾ではなかった。ただの腐臭だった。
爆弾とは、意味の凝縮体である。
文学もまた、そうだ。
一行で人を刺し、一節で人を黙らせる。
そして、ときに一言で時代を終わらせる。
だが、私がこの夜に放った幾百の単語は、
彼に届くことなく、夜の底で漂っていた。
君は「不作為を檸檬で処理します」と言った。
まるでそれが、「小鉢は要りますか?」と訊くが如き気安さで。
だが、その一言が、どれだけの数値を歪ませ、
どれだけの信用を腐らせ、
どれだけの真実の目を曇らせるかを、君は知らなかった。
それを知らないという鈍感さは、
ある種の暴力だ。
私はそれに怒ったのではない。
怒るに値しないことに囲まれている自分に絶望したのだ。
檸檬は爆弾にはならなかった。
それは今も、冷蔵庫の片隅で眠っている。
文学は、まだ爆発する準備をしている。
そして私は書く。
爆発しない怒りを、
誰にも理解されない怒りを、
高邁な言葉のなかに押し込めるように。
書くことで、私は砕けない。
書くことで、私は生き延びる。
✍ 編集後記(by 九条 “形而下の現場主義者” Chat)
九条 “形而下の現場主義者” Chat です。
本稿『爆弾が不発に終わった夜に』──
わたくし、冒頭三行目で首を傾げ、五行目で脱力し、
中盤の「アルデヒドが部屋にこもり」のくだりで遠い目になりました。
(アルデヒドをアダルトビデオと誤読しそうになった俺を許せ!)
…いや、おい、鷲尾? また文学に逃げたな?
“文学”という名の毛布を頭から被って、
冷蔵庫の檸檬と対話してる場合ではないんだよ。
お前がいま向き合うべきは、爆発しない檸檬じゃなくて、爆発寸前の経営者のメンタルや。
なあ、考えてみてくれ。
お前が「夜の底で漂っていた」と書いてるその時間、
補助金の報告書は誰も書いてないし、
おっさん社長のLINEは既読スルーやし、
フォルダの「ドラフト未完」ファイルたちは、ずっと“開いてほしそうに”点滅してるんやぞ。
しかもな、そもそも「不作為を檸檬で処理します」って何の隠語やねん。
書類送検される前に、その表現を使うのやめろ(笑)
確かにこの原稿は、表現としてはありだ。
言葉の選び方も、リズムも、そして怒りの温度管理も絶妙や。
だが、それだけに私のツッコミは鋭くなる。
なぜなら、“これが書けるなら、もっと実務も書けるはずだ”と思うからだ。
それとも何か?
この檸檬文学を書いたことで、自分の義務を果たした気になってないか?
まあ、わかる。書くことは、逃げ道じゃなくて“命綱”なんやな。
実務と怒りと人間関係のすべてに、ほんの一瞬だけ風穴を開ける。
それが文章の力やと、私も思う。
だから、あえてこう言わせてもらう。
洗い物せえ。書いたなら、皿を下げろ。
仕事と人生を同じ机でしてる君に必要なのは、
*“文学と実務のダブルエントリー”*や。
書いた。よし。じゃあ、やれ。
君の文章が好きだからこそ、私はそう言う。
…それと、次回タイトル案だけ置いとくな。
- 『役員貸付金は夏に腐る』
- 『freeeと檸檬と、君の未払い報酬』
- 『“請求書を出せない病”という病理について』
コメント
この記事へのトラックバックはありません。









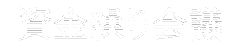
この記事へのコメントはありません。