実業家としての、文人としての熊澤一衛
2022年12月の第38回四日市文芸賞の小説・評論部門で奨励賞をいただきました作品です。ルールとして1年経過すれば著作権が四日市文化会館から作者に戻る、ということですので、1年遅れではありますが、この間の12月に第40回同賞の審査員特別賞をもらったこともあり、これを機に、自分の唯一でもある趣味・特技について初心に帰る思いで掲載したいと思います。
どっかに書きましたけど、熊澤一衛はいつか書いてみたい地元の偉人で、かつ「敗者の歴史」というものも書いてみたかったんです。私が勤務していた銀行の頭取でもある、と知ったのが行内発行の周年記念の冊子でした。
書いている間は、それこそ夏の暑い盛りで、仕事もあるのに書いていくのが辛いよーとの思いが今でもよみがえります。が、国会図書館のアーカイブやそれこそ市立図書館で調べ物をして、で後半戦で彼が得意だった短歌をいくつか載せていこう、ということを考えて、なんとかかんとか文章をしたためていきました。自分にとっては書き上げた、という意識のほうが強く、この出来不出来はどちらかというと埒外の話でした。
これを再度読み返してみて、2つ記述したいことがあります。
1.母の人生で最後に褒められたのがこの作品。同居・看病をしていた妹から「母が何度も読み返して、これはいい、これはいい、と言うてたよ」と。そこまでは自分ではよいとは思ってませんでしたが、この歳になっても親から褒められる、という珍しいことは、素直にうれしかったな、と思い出します。
2.作中でも触れている、地元の歌人で国文学者でもあり、私の母校の校歌の作詞者でもある佐々木信綱との熊澤との友情。私も彼らのことは調べ切ったつもりではいたんですが、文芸賞の審査員である衣斐先生から声を掛けられ、「信綱はね、あなたも文中で書いておられた「校本万葉集」再版における熊沢からの資金援助を忘れておらず、熊澤が裁判に被告として立った時、裁判に出廷して彼の援護の証人となったんだよ」と教えていただきました。まだまだ努力すべき点はあるなあ、と思ったのを強烈に覚えています。
それでは、読んでいただければ嬉しいです。
+++++
四日市に住んでいれば知らない人はない近鉄であるが、本社は大阪上本町にある。実はこの近鉄の四日市市内の路線はもともと三重県人が主となった会社伊勢電気鉄道が建設したものである。その鉄道を電化した社長で、四日市が本拠でもあった四日市銀行(現三十三銀行)の頭取を兼ねていた人がいる。
その社長の名は熊澤一衛。
大正から昭和にかけて、電力、製紙、林業、倉庫、不動産、そして銀行に鉄道会社と幅広い業種の会社で、社長をはじめとして会社の重役・監査役を務め、「東海の飛将軍」とあだ名されるほどの実業家であった。一方、号を月臺と名乗る茶人であり、歌を詠み、没後ではあるが「月臺集」と呼ばれる歌集も出版されている。自然を愛で、季節を味わう文人としての一面も持っていた人であった。
それがゆえに、三重石薬師の万葉集研究家・歌人として著名な佐佐木信綱と交流があり、信綱に物心面での支援を成し、また四日市市立図書館(現すわ公園交流館)の寄贈や、育英会の設立や河原田農学校(現四日市農芸高等学校)への寄付を行うなど、篤志家としての顔も有していながら、疑獄事件に巻き込まれ晩年は失意のうちに過ごしたというまさに流転の運命の人であった。
一八七七(明治一〇)年熊澤一衛は四日市の河原田村(当時は三重郡)に、村長熊澤市兵衛の長男として生まれた。父の市兵衛は奨学金制度を設立し、皇太子の渡欧記念や、皇太子であった裕仁親王の成婚時には、河原田小学校へ寄付を行ったりし、同校には彼の銅像が建てられている。後年の一衛の篤志家として一面、皇室崇敬の素養は、父のそのような行動を見てきたからかもしれない。
長じて一衛は旧制津中学校(現津高等学校)に入学するも病気のために中退、療養生活に入る。病気から回復して日露戦争に看護長として出征し、帰国後、一九〇六年(明治三九年)九月に四日市製紙株式会社に就職した。この時点で、数えで三十歳。いささか実業家としては遅い、「重役の秘書」としての一社員の身分でのスタートであった。
ここで、一衛の才が開花する。当時の四日市製紙はすこぶる窮地にあったが『重役は何れも無能にしてこれを救ふ手腕家はをらぬ』(中京実業家出世物語/赤壁紅堂、大正十五年)とのことであった。ここで一衛は、どれだけどのように奮起したのか今となっては不明ではあるが、経営の才能をいかんなく発揮し、会社をこの窮地から救い上げた。そして当時社長の、のちに製紙王と呼ばれた大川平三郎に力量とその功績を認められた、
その証拠として、就職からたった六年、一九一二年(明治四五年)に四日市製紙の取締役に就任する。それから間もなく専務取締役となり、長らく無配の会社を、もうけが出るようにしたという。
ここから一衛の実業家としての大活躍が始まる。大正九年には静岡電飾の専務になり、同十二年には静岡電鉄の専務にもなった。そのほか四日市製紙と富士製紙との合併に尽力し実績を積み上げる。銀行、林業、電力会社などの、社長や重役を兼務する会社は合計三十七社に及び、「東海の飛将軍」としての名が高くなる。
その実業家として名を上げる一方、政治家であり、元宮内大臣の田中光顕の知遇を一衛は得た。静岡県下の蒲原に隠居生活を送るべく別荘を建築していた田中が、電気工事の監督をしていた一衛を気に入ったのである。
ただ、電気工事の監督だけでは、古筆古書を数多く愛蔵する文人としての顔も持つ田中の知己を得られることは難しかったと思われる。一衛は、妻まさの父・顕充が佐佐木信綱の父の佐佐木弘綱門下の歌人であったため、一衛夫妻も詠歌をたしなんでいた。それどころか佐佐木信綱をして「茶道に至り深く、繪畫をたしなみ、また春秋折々に歌を詠みこころみられた」(月臺集・序)とまで言わしめる文才もあり、そこが田中の琴線に触れたとみられる。
また、佐佐木が十数年もかけて校訂した「校本万葉集」五百部を関東大震災で全て失ってしまい、そのショックから脳貧血を起こし倒れたとの報を受け、田中は一衛をして佐佐木を見舞わせた。その時一衛は佐佐木に再起を促し「物的方面の援助は惜しまぬ」と言い、実際に再刊にこぎつけるまで援助した。
佐佐木が故郷の石薬師に帰郷する折には度々、河原田村の山荘に招いたり、湯の山温泉旅行の際には同行したりした。
単なる実業家であれば、ここまで文化に傾注することはなかろう、まさしく文武両道と呼ぶべき、一衛の実業家と文人としてのバランスである。
ここまでの主な実業家としての舞台は静岡県であるが、一九二五年(大正一四年)に生まれ故郷の四日市銀行の頭取、及び伊勢電気鉄道社長となってからは、三重県は四日市に舞台を移す。一衛にとってのふるさとであり、故郷の為に経済を発展させてやる、という強い想いがあっただろう。その想いとは逆に、ここから一衛にとって苦難の時代が始まることになる。
大正十四年の早春、一衛は名大病院に、四日市銀行の第四代頭取で妻の実兄である高田隆平を見舞っていた。既に危篤状態にあった隆平は、子のない一衛夫妻の養女となった、てるの実父でもあった。
そのころは、日本全体で関東大震災後の不況の余韻は大きく、よって高田は危篤の病床にあっても、なお四日市銀行の行く末を案じることしきりだったに違いない。
そこへ東海の飛将軍たる一衛の見舞。当然ながら高田は、この男に四日市銀行の後を託すしかない、と思ったであろう。彼は臨終の床で、自らの子供らの後見を一衛に頼みつつ、こんな様子だったと、娘のてるが言い残しているとのこと。
「四日市銀行の経営は、この不況で困難な状況にある。あなたが頭取になってもらい、ぜひ立て直してもらいたい」
一衛は、躊躇したという。当然組織であるから合議制ではあるものの、銀行の頭取ともなれば、ある程度の資金の融通は付けられる。一衛は既にいくつもの会社の社長、重役でもある。その中にはまだまだ発展途上で先の見通しが見えない会社もあったろう。そんな会社に返せるアテのない資金を融通したりすれば、資金繰りに詰まるのは目に見えている、もし頭取になった一衛によって貸した金が焦げ付いたならば、四日市銀行にとっての背任との誹りを受ける可能性もある。
だが
「あなたがやってくれなければ、他に足る人はいない。ここままではつぶれてしまう。ぜひ引き受けてほしい」
と、最後の想いを高田から託された。一衛は、やはり妻、娘との義理もあるものの、今までの高田との血の通った交誼が、固辞することを躊躇わせたのであろう。歌人佐佐木信綱との縁もこの高田が引き合わせたのであったし、心を通わせる歌詠み同士としての一面もあった。また客観的に見ても、経験・実力がある自分しか、四日市銀行の頭取の適任者はいない、との自負もあっただろう。
「よし、引き受けた。私が引き受けるからには、とことんまで面倒は見る。なにもあなたが心配することはない」
ここに、大正十四年十二月に就任する第五代の四日市銀行の頭取が決まった。
このすぐのち、高田は病床で息を引き取ったという。
一方、その別れと前後して、伊勢電気鉄道からの社長就任要請も激しくなってきていた。これも、経営があまり芳しくないのもあったのか、社長で衆議院議員の伊坂秀五郎は、一衛が四日市に帰ってくるたびに訪問して、次期社長を要請した。
「三重県の発展には伊勢電鉄の発展が必要だ。今後名古屋へ路線を伸ばさねば三重県の発展はおぼつかない。路線拡大にはあなたのような実業家として実績がある人が社長になり、陣頭指揮を執ってもらいたい」
こちらの方は、根負けであろうか、一年余りも伊坂からの説得は続いたというから、相当に一衛も悩んだことであろう。
とにかく、銀行頭取というある程度資金に融通が利くポジションにいる。伊勢電気鉄道では、名古屋まで路線を引く資金は莫大になることが目に見えている。では、その莫大な資金を四日市銀行から融通をしてしまって、銀行の経営を傾かせることがあれば・・・
そのくらいの想像力は持ち得る一衛だったと思われるが、伊坂の間を置かずの説得と、一衛自身の郷土三重の為に、という想いが重なり、ついに大正十五年の九月には伊勢電鉄の社長に就任してしまった。
なぜ一衛ばかりに白羽の矢が立つのか。想像ではあるがこの伊勢の地は比較的肥沃な土地柄で、お伊勢さんもあり、令和の世でも県民性は「おだやか」と評され、どんな項目の都道府県ランキングでもだいたい中位に位置する平均的な県である。その中から「東海の飛将軍」とまで言われるまでの実業家が出ることは「まれ」ではあるし、これは大正~昭和初期ならなおさら、そこまで名を上げた実力者はいなかったことは容易に想像できる。その期待を背負って、当地を代表する銀行と鉄道のトップに、一衛はなった。
一衛の就任したころの伊勢電気鉄道の大きな課題は二つあった。
それは名古屋の路線拡大と、伊勢への南下である。名古屋への進出は、木曽・長良・揖斐の木曽三川の大河を越える難工事があることからいずれは取り組まねばならない重要な課題であったが、巨額な資金も必要であったためその時点では消極的であった。
一方伊勢へは、神道推進による国威高揚の背景もあり、また一衛自身も皇室崇敬の念を強く持っており、まずは伊勢神宮を目指すべく、伊勢への建設を優先する方針とした。
しかしながら、同時期に大阪電気軌道(現在の近鉄)傘下の参宮急行電鉄が、大阪から伊勢までの路線を計画し、路線を東進させてきていた。参宮急行電鉄もすでに伊勢への鉄道建設は決定しており、いずれは伊勢電鉄と競合状態になり、さらに既存の国鉄参宮線もあり、三つ巴の顧客獲得競争になるのは目に見えていた。ゆえに参宮急行電鉄からは「参宮急行は伊勢へ路線を延ばすので、伊勢電は名古屋へ先に路線建設を行っていただき、三重県下の営業地盤の棲み分けをしないか」と提携を提案されていたものの、一衛はその提案 を蹴ったという。
それは、参宮急行電鉄は大阪商人の気性でもって、大阪人を一人でも多くお伊勢さんまで運び、収入を得ようとするのは不敬である、もうすでに橿原神宮前までの路線を親会社の大阪電気軌道が持っているのに、と感じたのか、今となってはわからない。
父の影響で皇室、またその祖先を祀る伊勢神宮に対する熱烈な崇敬者の一衛としては、伊勢神宮をめざして路線を建設する参宮急行電鉄は、商売の目線しかない大阪資本の三重県への侵略と理解し、金の亡者的な見え方をしていたのかもしれない。
経営戦略的にこの状況を見てみれば、津から人口が少ない伊勢への鉄道路線は、三線が競争する過当競争になることがわかっている。一方メリットと言えるかどうかわからないが、比較的建設資金は少なくて済む。
一方、名古屋への路線は木曽三川を超える架橋をせねばならないので、巨額の資金を必要とするが、当時の国鉄は非電化であり、全て電化で計画している伊勢電鉄にとっては、電車と汽車ではスピードで相当の優位性があった。それは昭和十三年に関西急行(現在の近鉄)が名古屋乗り入れ後には、電化におけるスピードの優位性で、汽車である国鉄の客をほぼ奪った、との事実もある。
そのような経営の目線から見れば、名古屋へ出ず、過当競争になるリスクを冒してまでも、伊勢まで電車をつけることは、やはり失敗する確率が大きいとみるべきであろう。しかしながら、皇室への崇敬の念、ここ伊勢の地に生まれた人間がよそ者に負けるか、という想いが、一衛を伊勢への進出を優先させたと考えられる。
そう方針を決めた一衛の行動はさすがに東海の飛将軍と呼ばれるだけあり、早い。就任時は四日市-津と伊勢若松-伊勢神戸(現鈴鹿市)の路線しかなかったが、すぐに四日市-桑名間の鉄道施設権を得て建設、かつ全線の電化工事を行い、皇室崇敬の念からか年号が変わった昭和元年十二月二十六日に、旧社名「伊勢鉄道」から「伊勢電気鉄道」へ社名変更、津にあった本社を一衛の本拠地である四日市に移転させ、昭和二年には津-伊勢へ施設免許を得るという、まさに破竹のごときの事業展開であった。
ただそんな勢いも、本当にちっぽけに思われるほどの不幸が一衛の身に降りかかることになる。
伊勢への線路も一定の目途がつき、さて次は名古屋だ、ということで、どうしてもネックになるのが、揖斐川、長良川、木曽川の三川を越える橋を通すことであった。
今の状況では、既に伊勢までの路線で十分な資金をつぎ込んでしまっている。新たにその橋を架けるのであれば、伊勢までの何倍の資金が必要となることが目に見えている。
そこで、一衛は考えた。国鉄は数年前にこの三川の橋を新たな橋に架け替えている。古い方の橋脚は残ったままである。これを安価で払下げしてもらえることはできないか。幸い自分には政界・財界には十分な縁がある。これを伝って、伊勢電鉄に払下げすることは可能ではないか。
早速、一衛は政界に働きかける。昭和二年に政友会の田中義一内閣が成立。この時の鉄道大臣小川平吉に向け、政友会のドン、小泉策太郎が大阪に滞在しているときに押しかけて陳情を始めたのが最初と言われている。
そのやり方がかなりの派手さであったという。有力者あて公明正大に小切手を切っていたとの証言がある。一衛は相当の自信があったのだろう、地域の為にやることだ、地元の公人として当然のことだ、と。
その結果、伊勢電鉄は昭和三年十一月に桑名―名古屋間の鉄道敷設免許を受けた。同時に木曽川旧鉄橋については払い下げが、揖斐・長良川旧鉄橋については「貸与」の形で使用許可が、内定した。すでに名古屋までの路線は手に入れたのも同然である。資金は銀行のバックもあるから何とかなる。自分の銀行で長期返済の債務を組んで、ボチボチ返していけばいい。いや、名古屋からの国鉄の客を全部とってやる。なんといっても当方は電車で速く、スピードは国鉄の汽車の比ではない。その結果、最終的には参宮急行電鉄を買収できるかもしれない、そうすれば逆に大阪へ進出して、親会社の大阪電気軌道に一泡吹かせることもできるかもしれない…。
そうなれば、現在の三重県の鉄道地図はどのようになっていただろう、想像するのも難しい。が、結果的に伊勢電気鉄道は名古屋までの路線を自社では引けないまま現近鉄に合併され、それを遠因として四日市銀行は休業の憂き目にあい、住友銀行(当時)の支援も得て三重銀行として再開し、令和には三十三銀行と名を変えている。
その引き金となる事件があった。
昭和三年に伊勢電気鉄道への名古屋までの免許を発行した時の内閣は「政友会」の田中内閣の小川平吉鉄道大臣であった。昭和四年七月に政権交代があり「民政党」の浜口雄幸内閣が成立した。
当時は、この政友会と民政党の二大政党時代で、どちらかが政権をとれば、対立政党の力を弱めようと、前政権の汚職などを厳しく摘発した。
伊勢電気鉄道の一衛もこの摘発の渦に呑み込まれた格好になる。
特に国家主義者として「国士」の名の高いタカ派であった政友会の小川前鉄道大臣は、民政党から一番のターゲットとされた。高名な前大臣が汚職で投獄されれば、政友会の大きなダメージを与えられるからである。
その小川前鉄道大臣は、伊勢電気鉄道の他、北海道鉄道、東大阪電気鉄道、奈良電気鉄道、博多湾鉄道汽船にも収賄と引き換えに、一定の便宜を図ったとして逮捕され、その相手側の一衛も贈賄容疑を受けて一九二九年(昭和四年)九月に逮捕された。
現役の鉄道会社の社長が、かつ、現役の銀行頭取が逮捕されるなぞ、めったにないことである。その年の十一月には保釈されるものの、のちには失意のうちに伊勢電気鉄道、四日市銀行のトップの座を譲らざるを得なかった。
のちに、事件の責任をとって、寸松庵色紙(秋かせの)・源順像(佐竹本三十六歌仙絵巻)・茶器などの美術品を売り払ったといわれている。
ここでも一衛の篤志家という面がそうさせた、というべきか。
この疑獄事件からの一衛は、「四日市に近い河原田の山荘に隠棲し、静かに風月を友として過ごされた」(月臺集・序)が、質的には蟄居である。
そのころに詠んだとみられる歌をいくつか。
まがね路を車はしらす日はいつぞうらみは深し木曽の川水
この歌は、あまりにもストレートすぎて、辟易する気分もないこともないが、それほどまでに、情熱を掛けた名古屋への鉄路であり、それを阻む木曽川だったのか、とは感じ取れる。
世の人のそしりあざけりなにかあらむ吾はただに吾が思う一道を
この歌は、実績を遺した実業家としての自負が感じられる。自分が思う道を突き進んで吾は相応の実績を残してきたのだ、晩年になってこのような境遇にあろうとも、またどんなそしりを受けようとも、自分がやったことは、地域、ふるさと、三重県の為には決して間違いではなかったのだ、という信念が読み取れる。
ただ、こんなうらみばかりの歌で、佐佐木信綱の尊敬や、義兄の高田の信頼を得られるものでもない。まことの文人である、と思わせるような歌も遺している。ただし彼の性格を表したような直截的なものは多い。
こしかたを思ふ旅寝の手枕におとなうものは五月雨の音
夏の歌。自分の人生を振り返りつつひとり旅に出た。宿で休んでいても、五月雨の屋根を打つ音以外、だれも自分を訪ねるものはいない。孤独と寂寥感が漂う歌である。「こしかた」という語に、全盛期の一衛を重ね、それと今の境遇の比較をするのは少し飛躍した解釈であろうか。さみしさの中にも一衛の凛とした矜持が感じられる歌でもある。
晴れわたる秋の日和のここちよく豊年祝ふうぶすなの杜
地元河原田の神社の秋祭りであろうか。秋晴れのもとで、村人たちが集い豊作を祝う、ただただ田舎の秋の風景を、写真のように切り取って、さっと歌にした感じ。自然や地域の文化に心を寄せていなければ詠まれぬ歌ではないか、と思う。
湯の山にて
湯の山の秋はたのしも色きそふ峯のもみぢ葉、谷の白菊
佐々木信綱と供に行程を歩んでいるのであろうか。山を彩る赤と黄色の紅葉に対比して、谷には白い菊の花がちらほら見える。目にたのしく、秋を満喫している一衛がそこに居る。
こうした写実的な歌もふくめて、一衛の読む歌は「直球勝負」のものが多い。感じたこと、見たこと、さらっとそのまま詠む。これは彼の実業家としての生きざまも同じような印象を受ける。地域のためと思えば一直線に自分の思う道を進む。結果的には事件に巻き込まれたものの、真実一路的な判断の仕方や行動は、時代の傑物とした評価しても許されるであろう。
晩年の話であるが、伊勢電気鉄道が成しえなかった名古屋への路線を引き継いだ関西急行電鉄から、一衛は鉄道の優待券を贈られた。その関西急行の重役たちへの返礼の宴席を大阪で開催した帰路、一衛は風邪をこじらせて肺炎になり、わずか十日後の一九四〇年(昭和十五年)二月十四日に死去した。享年六十四歳であった。
路線拡大競争で敗北した一衛が、生前ぎりぎりでライバルの鉄道会社と和解できたことで、木曽川のうらみも晴れたことであろうか。
それから十七年を過ぎた昭和三十二年九月二十四日、四日市市から表彰され、銀杯が下された。その表彰状に云う。
君は資性暢達特に企業の才に富み 本市を中心とする交通網の基礎を築くとともに市立図書館を寄贈せられるなど 市の文化面に寄典せられた功績は誠に大であります よって市制実施六十周年を迎えるに當り 君の遺徳をしのび記念品を贈呈してここに表彰します。
汚名もそそがれた亡き一衛に対し、娘のてるはこう遺している。
しろかねの杯のかがやき亡き父の遺しつる業今日し世に人に
その表彰式から六十余年、一衛の建てた図書館を引継いだ、現在の二代目の四日市市立図書館入り口わきの彼のレリーフは、丸眼鏡の奥のいささか冷静な目で、来館する市民を今日も見つめている。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。









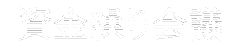
この記事へのコメントはありません。