或る老職人の晩年

この作品は、おととし十二月、四日市文芸賞の特別賞をいただいた作品(リンク先は1年近く前に感想書いたやつです)である。
受賞から一年が経ち、市の著作権の扱いも整理がついたようなので、
この場に全文を掲載することにした。
もともと、広く読まれることを前提に書いた作品ではない。
だからこそ、PDFをそのまま置くのではなく、
読んでやってもいい、という人が読める形で残しておきたいと思った。
この作品には、現実のモデルがいる。
ただし、これは記録ではなく、物語だ。
受賞の知らせを聞くより前に、
モデルとなった人物は亡くなった。
生きていれば、どう受け取ったのかは分からない。
さらに言えば、その後、遺族の方々との関係も途切れた。
特別な対立があったわけではない。
現実というものが、ただ、そういう形を取っただけだ。
この作品は、
いくつかの「うまくいかなかった現実」を、
あとから意味のある順序に並べ直したものでもある。
現実は、たいてい物語のようには進まない。
人は、自分が思うようには動かない。
それに対して腹を立てる年齢は、もう過ぎた。
いまは、いとおしさと、諦観が、同時にある。
以下は、そうした感情の上に書かれた、ひとつの物語である。
読んでやってもいい、という方だけ、どうぞ。
或る老職人の晩年
第40回四日市文芸賞応募作品
Ⅰ
商工会議所の朝は意外と早い。官公庁と同じ八時半に業務開始だ。でも、開始後しばらくは訪問者が来ないのが常だ。
ここで週三日のペースで働く私は、元信金マンでもあり、会員の経営の相談に乗ったりする専門家として詰めている。三年前に地元の信用金庫を四十九歳で辞め、そのまま実家の寺の住職に専念しようと思った。が、ある若いころからの根本的な疑問を解消すべく、この商工会議所の経営指導員として応募し、希望したポジションを図らずも得ている。
この仕事を遂行しつつ、檀家の不幸とかがあれば高齢の父とうまくやりくりした対応は行っている。そんな感じの私の第二の人生は、妻も最初は不安がっていたもののそれも収まり、同じ年ごろの壮年の男としては恵まれた人生だと思っている。
いつも通り、同僚とあいさつを交わし、手帳を開き今日の予定を確認する。午後からしか面談の予定はない、急な不幸でもあったら別ではあるが、実家の法事の予定も来週までない。少し溜まった残務を朝のうちに片付けられるかな、と思ったが、その通りにはならなかった。
グレーのつなぎの作業服の小柄なご老人が、入口の自動扉を用務員さんが開けるのと同時にすたすたと入きて、若い経営支援員の栗沢君の名を呼ぶ、大きな声だ。呼ばれた栗沢君はああ、赤元さん、などと応えながら、カウンターに誘う。彼は老人と向き合って座ることになる。
その様子を私は横目で見ながら、仕事に入ろうか、と思った矢先、
「前園さん、ちょっと相談があるんですが」
と、私に声がかかる。
やれやれ、手元の資料を机の端に軽く片付け、栗沢君の隣に並んで座る。私もカウンターを挟んで向き合って座ることになる。
「前園さん、この方は・・・」
「私からあいさつしますわ、私赤元機電工作所の代表の赤元源蔵といいます。実はですな、腕を怪我して動かんようになってしまったんですわ」
と、またこれも大きな声で自己紹介をする。
「古くからの当商工会議所の会員さんで、記帳指導とかさせていただいて折々には商工会議所へ来てらっしゃる方なんですけど、体を悪くされて、事業の存続も真剣に考えておきたい、とおっしゃって」
栗沢君の説明を遮って、赤本氏は言う。
「それでですな、この腕が治ったあかつきには当然事業は再開するんですが、わしには借金がある。今七十七ですがな、百まで生きるつもりではおるんです。けど、なにぶん色々と問題がありましてな」
独特の明るさを持ったご老人だな、と感じると同時に何らかの頑固さ、それは、こだわりを持って仕事をしてきた男の誇りとも感じられる。
「昭和二十二年四月の伊賀の生まれでしてな。新設高校の機械工業科の二期生として卒業して、機械製造工場に勤めたんですわ。自分ではアイデアマンと思ってまして、社内業務開発賞を三度も受賞しました」
饒舌にとめどなく話を続ける赤元氏である。
「上司の紹介で見合い結婚をして、子供も生まれまして、月賦を組んで家を買って今でも住んでます。そのころにわしのアイデアをほめてくださる協力会社の社長がおりましてな、君は工場勤務で留まる人間じゃない、自分の思うような機械や工具を作って、我々みたいな多くの中小企業の社長と一緒に対等の立場でもっといいモノを作ろうじゃないか、おっしゃってくれまして、銀行の支店長まで紹介していただきまして。今までお世話になった工場を辞める、ということは義理も欠くことになると思ったんですがね、『あの工場では赤元君の代わりはいるが、市井の工場の社長と一緒に知恵を出し下請け工場の効率を高められる技術とアイデア、そしてそれを考える頭脳を持っているのは、赤本君、君しかいないんだ』なんていう言葉にグラッと来て、独立することを決意したんですわ」
そこから、赤元氏はこんな話をした。
彼は、紹介された銀行から借金をして土地を買い、工場を建てた。時は日本全体が高度成長期で、細かい製品の製作や、機械工具の修理など、その社長を始めとしたいろんな工場から、ゲップが出るほど仕事を請けた。誇張ではなく朝から晩まで、月月火水木金金で働いた、当然結果として、お金は儲かった。
五年ほどして工場の借金は全部返した。ついでに家の月賦も完済できるほどのお金も稼ぐことができ、名実ともに自分の家となった。
その頃、前職の会社でかわいがっていた後輩が訪ねてきた。かなり優秀で技術も頭も冴える奴で、赤元氏が独立したあともつかず離れずの仲でなにかと世話を焼いてやっていた。バブル経済が崩壊し、日本全体が不況に突入した時期に後輩は会社を辞めて自身のビジネスを立ち上げる決意を固めた。彼は新しい製品の開発に必要な資金を求めて赤元の元を訪れ、どうしても資金が必要で、手形を切るから三千万円を貸してほしいとの話だった。赤元氏は彼を信じて、その大金を貸すにした。彼の新製品開発は順調に進んでいるように見えた。が、次第に資金繰りは悪化し始めたようだった。返済も最初はきちんと行われていたが、ある時期から突然連絡が途絶えた。一応彼の自宅も訪ねもしたが、家族も居ず、もぬけの殻だった・・・。
「なぜあなたは手形を取立に回さなかったのか?」
私は不思議に思い、赤元氏に尋ねた。
「そんなことしてもしゃあない。家に誰もいないのならもう返すつもりがないだろうし、金もないはずや。手形を回しても不渡りで付箋がついて戻ってくるだけや。でもな、因果応報、輪廻転生、地獄で痛い目に合う、かえってそれでわしは徳を積んだ。わしはその手形を残してあるんやけど、最近はその手形が神社でもらったお札のように思えてきて、ありがたいことやなあとか思ってます」
赤元は本気か冗談か分らぬ表現で答えた。
その三千万円を貸したせいで赤元の資金繰りは悪化したが、まだ銀行からの信用は残っていたようで、工場を担保に差し出したうえで同額の借金を抱えた。その頃から世の中の景気は急速に冷え込み始めた。高度成長期の熱気が嘘のように消え、赤元の工場も次第に仕事が減り始めた。生活は何とか維持できるものの、経済的には厳しい状況が続いた。貸した三千万円は戻ってこず、赤元の借金は増えたり減ったりを繰り返し続けている。
「今でもその借金のうち、まだ二千万円が残ってるんですわ。おまけに最近は怪我してしまって、思うように仕事ができんようになってしまった。売上自体は順調なんやけど、どうもわしは人が良すぎるようで、いつも仕事をかなり安い金額で引き受けてしまうんですわ。そのせいで、利益があんまり出ませんでしてな」
赤元の声には疲れが滲んでいたが、その目にはまだ光が宿っていた。
「でも、地元の人たちにはえらく受けがいいんですわ。皆さんが頼りにしてくれるのは嬉しいんやけど、それが儲けに繋がらんのが現実ですわ」
赤元氏は続けて、地域社会への自分の貢献について語り始めた。彼は長年にわたり、地元の中小企業や個人事業主を支えてきた。彼の工場では、機械の修理やメンテナンスを安価で提供し、多くの事業者がその恩恵を受けており、彼のアイデアと技術は地元の生産性を大いに向上させていた。
「例えば、あの徳山さんの印刷所、もう十年以上前になるけど、市役所の広報を印刷中に機械が壊れてしまったことがあってな。古すぎて部品があらへんからわしが代用品を急ぎで作ってやって、事なきを得たということもあったしな。それに工務店から工作機械を直してくれ、とかの注文も多くて、皆さん困ったときは真っ先にうちを頼ってくれる。使い捨てじゃなく修理して使うことはええことやし、今の時代に合っとる」
彼は微笑みながら、地域の人々が彼を支える姿勢についても触れた。
「最近ではわしが腕悪くしたって聞いて、他の工場の若いもんが手伝ってくれたりしてな。本当にありがたいですわ」
黙って赤元氏の話を聞きながら、彼の背負った地元からの深い期待と、応えるべく行動している様子を聞き、地域の人々が彼をどれだけ愛し支えているか、また十分な信頼をしているかが、私にははっきりと感じられた。
「話が長くなってしまいましたけどな、体も悪くしたのでこれ以上溌溂と仕事が出来ないかもしれません。だから勝手を申しますが、長らく寄り添ってもらった妻に相応のお金を残せる算段はありませんかな。さらに欲を言えばわしの仕事を継いでくれる人を探してもらえませんかな」
Ⅱ
赤元氏が帰られてから、私は残務を一通り終えた後、自分のデスクで彼の半生を頭の中で反芻してみた。かなりのお人よしではあるものの、頑固なところもある。それは自分ともよく似ている、と自分の半生を思い返してみる。
私は浄土真宗徳福寺を守る住職前園家の長男として生まれた。代々、徳福寺は自作農家をやりつつも、伝江戸時代作の阿弥陀如来を本尊とする大きなお堂を開放し、特に祖父は、月に一度農産物の交換会や自らの説話会、はたまた檀家さん以外も含む地域住民の悩み相談室まで、ボランティアでやるような男だった。必然、寺は地域住民のたまり場になっている。父は学校卒業後、公務員として市に奉職していたが、祖父が他界した二十五年前に辞職し、住職専業になり、祖父の意思を継いだのち、新たに保育園の経営も始めた。
幼いころから私はそんな祖父や父親の背中を見て育ち、自然と仏教の教えや寺の務めを学んでいった。とともに前園家の、いや自分自身の役割とは、地域社会に貢献することである、と何とはなしに考えるようになった。
成長するにつれて、寺院とは、地域の方々に生まれてから死ぬまで寄り添う意義ある仕事であると徐々に感じるようになってきた。
加えて特に檀家の方々からも、寺の跡取りといわれ、将来は祖父や父のように、地元に根を生やし地域に貢献する人物になりたい、と自然に思うようになった。
しかし一方で、祖父や父のやり方は何か違う、とも感じていた。例えば保育園の経営がうまくいかない時期にお寺のお堂の大規模な改修工事もやってしまったものだから、経済的に困窮し、ご飯はお供えのおさがりのみ、例えば毎日大根の入ったおかゆみたいなので暮らした時期もあった。それは私の高校二年生の時だった。一方で、祖父や父からは、進学についても地元の大学、出来れば仏教系の大学へ行って将来の後継ぎとしての勉強をしてほしい、との強い要請もあった。
私には目立った反抗期はなかったので、お金を家に無駄に使わせることはしたくなかった。が、この選択の不自由さはどこから来ているのか?と考えるに、しっかりとしたお金の考え方を祖父も父も持っていないから、とも考えた。理論的・合理的な考え方を持てば、この経済的困窮状態は避けられたのではなかったか、そうした学問を習得すれば、うまく家計を回すことができるのではないか、たまに檀家のお布施の額が少ないと愚痴をこぼす祖父や父を見ていて、お布施の少なさだけが原因ではないのではないかと思っていた。
それを、祖父・父に正直にぶつけてみた。さすがに二人は憮然とした顔になったが、跡継ぎがそれほどまでに家のことを考えているとはと、何かを感じたようであった。さらに私は仏教系の大学には行くけれども仏教を専門とはしない、自分は経営学を勉強してみたい、そしてこれからの家計・お寺の窮地をできれば無くしてみたい、と言ってみた。
父はうなずいてくれたが、祖父は頑固だった。が、最後には学在学中に僧職免許をとることを条件に認めてくれた。
無事合格し経営学部に入った。祖父との約束の僧職免許も二年生の時に取得した。大学の専攻である経営学も一生懸命勉強した。自分で言うのもなんだがゼミの教授には、大学に残って研究職をやらないか、とまで言ってもらえるほど頑張った。しかしながら、経営の何たるかは理解できたが、それをどのように活用できるのか、困窮を避けるためにどのような実践があるのか、その答えは大学にはないと感じた。
一旦は父のように社会に出たいし、出来ればその答えが出るようなところに勤めてみたい、と思い、私は必然金融機関に目が行くようになった。
当時、就職戦線は売り手市場だったから、あまり苦労はしなかった。その中で強烈に地元の信用金庫が秋波を送ってくれた。最終的には寺を継がねばならないのだから、私の探求心に答えが出ればそれでよし、と思って軽く決めた。祖父・父は私が後を継ぐ、と言っているので就職先には寛容だった。
信用金庫の仕事は、最初は下積みであったが、五年ほどすると融資などの案件を任せてもらった。そこで財務分析や融資稟議などを通して、いかにうまく貸してうまく回収するか、ということをベースとして業務を覚えていった。
転機となったのは十年目の夏だった。取引先の一人親方の建設屋が、五十歳で亡くなった。当庫からの貸付金は五千万円弱あった。自宅の担保はあったものの到底五千万円にはおよばない、毎月の収入も限定的である。残された一緒に働いていた奥さんと大学生の娘さんがいたが、仕事を取ってくるご主人、また仕事を回す外注先に顔が効くご主人が居なければ、この商売は成り立たない。
ゆえに、私は奥さんに相続放棄を勧めようと思った。これはご主人の財産も継がない代わりに、債務も継がない、という法律的な制度である。奥さんには新たな職を見つけてもらう必要はあるが、従業員もいないし廃業も割と楽にできるし、なにより多大な債務をこれから背負わなくて済む。
私はそのことを上司に相談した。返ってきた返事は意外なものだった。
「あそこはご主人が居なくても、なんとかやれるだろう。奥さんだって得意先や外注先に相応に顔が効くはずだし、なによりもうちの貸付金が焦げ付くことになるのはごめんだ。こういうのは相続人の意思というものが大事だ、奥さんのご意思をよく聞いて、お前は余計なことを言わずに黙っていればいい」
だから、私は奥さんには相続放棄のことは言わず黙っていた。
ほどなく奥さんは跡を継ぐので、そのための手続きを取りたい、と申し出てきた。私は粛々とそれに応じ、手続きの時に、こう言った奥さんの言葉を信じて、そのまま放念してしまった。
「主人が亡くなって商売辞めようと思ったけど、まだ借金も残っているし、それは絶対返さなきゃいけない、って主人も言ってたし周りの人みんな言うのよ。生命保険も入ったし、私なりに頑張って主人の商売を続けていきます」
しばらくは、奥さんは営業活動を行っていたらしい。らしい、というのは返済が滞っていない事業者にわざわざ訪問してまで、営業活動を見に行く必要もないからだ。他にもたくさんやるべき業務はある。毎日営業時間後に取得する延滞先一覧表には奥さんの名前は出てこなかったし、返済をしている≒仕事は順調である、という判断をしていた。しかしながらこれは私の怠慢、といわずとまでも手を抜いていたのには間違いがない。ご主人が亡くなったばかりの時の奥さんの口座には、相応の残高があったのを記憶している。
が一年後、残高不足で借入金の延滞先一覧表に上がったときには目を疑った。そうなってから一年の預金の出入り明細を改めて見れば売上と思われる入金はほとんどなく、あってもわずかな金額であり、一方借入の返済や種々の支払いでそれこそ預金通帳から急速に流れ出ていた。それを悔やんでも後の祭りだ。
当然、それを確認するやいなや、私は奥さんの自宅に急行した。しかし生活臭はせず、呼び鈴を押しても誰も応答しない。悪いとは思ったがポストの中を覗き見た。もう数日くらいの郵便物が溜まっていたし、その中には消費者金融の督促状らしき手紙も混じっていた、が、奥さんの行方は杳として知れない。私は落胆してそこを去って帰店した。
当然、上司から叱責を受けた。曰く、与信管理とは日々のチェックが大事であること、担当先の預金残高は毎月見ておくこと、なにか異常な取引があれば上司に報告すること、外出した場合には自分の担当先に寄り道して様子を伺うくらいの機転を利かすべき・・・
上司がおっしゃるのはごもっともだ。金融マンとしての、あるべき姿ではある。
が、それを私が励行したところで私は奥さんを救えたのだろうか。根本の解決策は最初のところで、ご主人が亡くなった時点で、ご主人の事業を放棄、という選択もあった。それを選んでおけば、今回のような事故を招かなかった可能性は高かったと言い切れる。私はそれを上司に具申した。当庫の手間の煩雑さを避け、利益を優先してしまったことが一番の原因ではないか、ということを、それとなく伝えると、こんな反応が返ってきた。
「言い訳はするな、お前が管理を怠ったことは間違いないことだ」
この事件が影響したのかどうか、私はこのあと、事業先ではない個人取引が主たる支店に転勤となった。私には事業をやっている個人や会社に融資を任せることが難しい、と人事部が判断したのだろうか。それでも腐らず私は一生懸命仕事をした。と同時に、学生時代からの問いである、「経営を活用し、困窮を避けるためにどのような実践があるのか」というものも知りたく、中小企業診断士を取得、かつ母校で夜間に通って経営学修士まで取った。それが功を奏したのか、数年経ってまた企業融資ができる支店に私は移された。
そこで学んだことを生かした実践を、ある程度は発揮できた。お客に融資をすることにより感謝を示されたこともあった。
その一方でどうしても、お金を貸す、管理をする、だけでは助からないということもわかってきた。どんなに頑張っても、経営だけでない幅広い知識の有効な活用ができない限り、また知識を持っていても実践がない限り知識の持ち腐れ、となってしまう。勉強した経営学を含む知識を生かしてこうしたほうが良いとか、ダメなところはダメとはっきり言いたいと思うし、もっと強く社長に関与し積極的に経営に関わらないと業況は好転しないと強く思う。
しかしながら信用金庫の職員としては企業を支援するにも限界がある。あなたは優秀な金融マンかもしれないがお客様に説教するのはいかがなものか、そんな苦情まがいのことを取引先の社長から訴えられたこともある、一片の私利欲もなく社長に進言したはずなのに・・・。
そんなジレンマを抱えつつ信用金庫の仕事を継続することに強く限界を感じてきたのが四十代の後半だった。そして父が七十五を過ぎたのを機に、信用金庫を辞めた。まだまだ元気な父であり保育園の経営も軌道に安定しつつあったが、人に説教する以上、我が家の経営が芳しくなければ、経営を語る資格はないだろう。ただ家業であるお寺と保育園だけでは、自分の能力を社会に還元を仕切れない、よって地元の商工会議所の経営指導員枠に応募し、週三日の契約で勤務している、という私の現在である。
私にはそんな背景もあるので、そもそも考えようややり方によっては背負わなくてよい借金を背負った赤元氏にはなんとなく共感というような気持が芽生えていた。一見なんと不合理な老人であろうか、と切って捨てる人もいるであろう。ただ私も、例えば上司の、黙っていろ、という進言を守らず、例の奥さんにこっそりと相続放棄を耳打ちし、詳しいことは弁護士に聞いてくれ、と言うこともできただろうし、また逆に相続させ、最終的に破綻したとしてもうまく立ち回れば上司との対立を避けることもできただろう。そんなことを考えるとお互いに、不器用な人生を送る」人間であるところには、なんとなくのシンパシイを無意識に感じていた。
Ⅲ
とはいえ、百まで生きるとアテのない信念を振りかざし、腕が動かんようになったからと誰か後継ぎを、と赤元氏は言うが、早急に事業が承継できるものではない。私みたいに生まれたころからお前は後継ぎ、と言われ育てられた者であっても多少の抵抗を人生において示してきたのだ。
実際、事業の承継は難しい。日本全体の平成七年の中小企業経営者年齢のピークが四十五歳であったのに対して、平成二十七年の経営者年齢のピークは六十六歳だそうだ。今であればもっと年齢が上がっているだろう。赤元氏のように、わしはまだ若いと頑張っている経営者はたくさんいる。けれども、神様はすべての人間に等しく、永遠の命を与えてはいない。よっていつかは不本意にもそのポジションを去らねばならないし、この世に別れを告げなければいけない。うまくこの世を去れればいいが、事業を承継できず借金だけ残して残された家族が重荷を背負っているケースも少なからず私は見てきた。
聞けば赤元氏には、妻、娘二人があり、そのうち次女は東京へ嫁に行き、長女は大学で知り合って結婚した旦那と、赤元氏にとっての目に入れても痛くないような二人の孫たちと二世帯家族として、自宅を増築して同居している。赤元氏のその婿はごく一般的なサラリーマンで、工作所の跡を継ぐつもりはないし、それ以前に工作等に関する技術もない。
親族承継の線はなしか・・・と私は思いつつ、それほど問題は簡単ではないことに気が付いた。自宅は抵当には入っていないが、赤元氏の死後、借金が工場売却により処理されるとして、その売却代金で返済できない、すなわち工場の売却代金が借金残高より少なかった場合、相続をした家族たちがその残った借入を返さなければならない、という問題である。下手をすると相続をした財産である自宅を売却して借入を返さねばならない可能性もある。となると、赤元氏が残した家も他人のモノになる可能性があるどころか、自らの住む家もなくなってしまう。
これは、前職時代の建設屋の奥さんとよく似ているが、建設屋の奥さんはなまじ旦那の仕事に関わっていたこともあり、事業は継続できる、という思い込みが失敗につながってしまったが、そのような話にはならないにはしても、借金問題だけはついて回る。
「前園さん、お先に失礼します」
との声ではっと我に返る。栗沢君だ。
「ああ、もうそんな時間か?お疲れ様」
もう少し栗沢君も自分のお客として赤元氏のことを考えてもらえたらいいのに・・・と思いかけたが、私は彼の上司でもなく、これは私の問題だろう。
ちょっと行き詰った感もあったので、私も彼に見習い、職場を後にすることとした。
季節は中秋の名月も過ぎ、急に秋も深まり涼しくなった。
更けた夜の中で私は一人寺の本堂に入る。築百年はゆうに過ぎている寺の本堂は広く、その主であるこれも百歳は超えているであろう木造の阿弥陀仏と、燭を灯して向き合う。
こういうとき、お寺の跡継ぎに生まれてよかったと思う。一人深く考えたいとき、無になりたいとき、そして人生で悩んだ時、ここに来る。家人もそういうときはそっと放置してくれる、ありがたいことだ。阿弥陀仏に問いかけるでもなく、独り言のように今日の出来事、考えたことをそれとなく頭の中で反芻する。
赤元氏の言葉が頭の中でよみがえる。
「寄り添ってもらった妻に相応のお金を残せる算段はありませんかな。さらに欲を言えばわしの仕事を継いでくれる人を探してもらえませんかな」
課題はこの二点だ。相続の問題と、事業承継の問題だ。赤元氏も自身の身体に自信が持てなくなってきたので、そんな発言になったのだろう。
相続の問題は私にとって二十年前の失敗が教訓になる。今度こそ相続放棄を前提としての対応をしたい。その前に赤元氏から奥さんに自宅の土地建物へ贈与を行う。長く連れ添った夫婦間での贈与では、税金がかからない制度もあったからそれが使えるだろう。
その後、借金を何とか処理できる前に赤元氏が不幸にして亡くなった場合、工場が借入額よりも高い金額で売れるようであれば、財産と借金を相続してそれで返す。工場の売却が安い金額だったり、不調だったりした場合は、亡くなってから三ヵ月以内に相続放棄をすれば、奥さんと娘さん家族には、少なくとも自宅は残る。
もう一つの問題、事業承継については、こう考える。実際何を言っても今の事業の状況は赤元氏の人間性で受注が取れている状況である。これを、事業の承継をしたところで、赤元氏がいない限り、そのままの事業体で継続できるのはかなり難しいだろう。ここは割り切って、工場を単なる不動産とみなし、工場単体で売却させる必要があるだろう。赤元氏は借金二千万円の完済に加えて、奥さんに相応のお金を残してやりたい、との希望がある。出来ればこれを満たす金額で売却出来たらよいが、工場はかなり古く、かつこの辺の土地だけの評価だと借金が返せる金額で売れるかどうかも危ういところだろう。工場の中の片付け費用も考えるならばそこから安くなるだろうし、さらに工場はいらず土地だけが欲しい買主であれば、取り壊し費用分を鑑みてもっと安くと交渉してくるだろう。
借金を返し、さらには奥さんたちに相応の現預金を残してあげるためには、赤元氏とよく似た仕事をしており、そのまま工場として生かして使いたい、という買主を探す必要がある。
この二点については、出来る限り早く、同時進行で行かねばならない・・・と考えているうちに夜もさらに更け、半月は中空に浮かび、その光は南向きのお堂に深く差し込んできて、阿弥陀様のお顔を照らすようになっていた。
Ⅳ
次の日、商工会議所への出勤も、寺としての行事もなかったこともあり、赤元氏の工場を見ておきたい、と思った。できれば彼に会い、今後の方針を早く推進していくことが大事であることを強く伝えたかった。
私は考えが浮かぶと、すぐにでも実行したくなる性質である。車で十分ほどの赤元機電工作所は国道から横道に入り少し坂を上った先にあった。車を止め、軽く目に入った工場の第一印象は、乱雑の一言に尽きた。素人目からみて、果たしてこの工場内のガラクタ、もとい機械や工具、部品類を片付けるのに一体いかほどの労力と時間が必要かと具体的に考えようとして、やめた。
「こんにちは」
少し薄暗い工場内に声をかける。
間を置かず、赤元氏が奥から作業中の手を止めて顔を出した。
「や、これは前園先生ではないですか。こんな汚い場所に来ていただき、恐縮です」
「先生はやめてくださいよ、私は工場の中身のことは何も知らないのですから」
といいつつ、私の呼ばれ方は否定しても、汚い工場というのは否定できないな、と心の中で苦笑した。
赤元氏から私は、事務所らしきスペースに招き入れられた。そこも似たようなものだった。机に載った大量の書類をかき分けて隙間を作り、また年季の入った事務椅子にも工具がのっていたから、それを退けつつ、赤元氏と対峙した。
「新たな仕事も入りましてな、朝から作業をしとりました。しかしですな、こんなに早く来ていただけるとは思いもよりませんでしたわ。さてどんなお話しを聞かせていただけるのですかな」
私は、昨日考えたことを話した。このままでは赤元氏が亡くなった後、借金が残ったりすれば、下手をするとご家族の住む家もなくなってしまう。まず、それを防ぐために自宅を奥さんに贈与し、名義を奥さんに変えること、そうすれば最悪自宅だけは残ると。
もう一つはこの工場を赤元氏が元気なうちに売りに出し、借入金の残高以上で売れればそれでよし。不幸にも買い手が見つからなかった場合で、万一あなたが亡くなった時には、ご家族に相続放棄してもらうこと、の二点を話した。
赤元氏はこれに答えた。
「そもそも自宅は家族のために建てたんだから、嫁さん名義になって、嫁さんの家に居候するのはかまいません。工場は高い値で売れたらいいけれど、それも現世の欲と言う奴ですかな。売れて借金が残らねば、売れなくても家族に迷惑をかけなければそれでいいんですわ。ただ先生、先生がこうして相談して次の日に来てくださったのも神様か仏様のおぼしめしとも思えるんですわ、そう思うと隠し事はあかんですな。実はですな・・・」
そこからの話は、私にとっては青天の霹靂だった。赤元氏は急性白血病に侵されているとの告白だった。医者から余命一年を宣告されているという。
「昨日商工会議所に訪問させていただいたのもですな、先日来、腕が上がらんようになった以外にも、どうも体の調子が悪くて残された時間は少ない、ということも心のどこかで分かっていたからなんですわ。それなのに今日まで死に対する準備、残される家族に対する準備もせず、先延ばしにして、ほれ今日もお客様からの新しい仕事を請け負って、いそいそと、それでいてスピードは全盛期からしたらカメのような速さで作業をしとったわけですわ。今この仕事をしている充実感に浸っていたいという気持ちを優先して、近々死ぬという現実から目を逸らそうと思っていたんですな。しかしですな、先生が今日すぐにこちらにお越しになって、こんなアドバイスをいただきまして、これは、早よう死ぬ支度をせよ、という天のお告げとも思っております。本当にわしは幸せものですわ。先生にとってはお会いして二日目でこんな話をされるのもかなわんとは思いますが、どうかこの哀れな爺をなんとかしてやってください」
私は自分の仕事でもある「経営」に関わることと、家業である「仏教」に関わることとは全く別物と考えて生きてきたが、そうではなく人間の生きざま、死にざま、という面でどこかで結びついている、ということを逆に赤元氏に教えられた気がした。
赤元氏に提示した方針はすんなり受け入れられたものの、実行するのはまた別の話である。
奥さんへの自宅の贈与については、私がその場で、電話で彼の顧問税理士と相談のうえ、対処をすることとなった。名義変更は商工会議所に属している司法書士先生に頼めばいいだろう。
一方の工場の売却、これは一筋縄ではいかない。
赤元氏は言う。
「先生、工場を売ること、またわしが不治の病にかかっていることは、先生以外には極力漏らさんようにして欲しいんですわ。こんな田舎で誰かが知ったら、噂が一気に広がって大勢の方に余計な心配をかけてしまう。わしは他人に心配かけずにコロっと死にたい。もちろん必要最小限の人達に相談するのはかまいません。だけど不治の病にかかったから売りたい、と大っぴらに広告を出すのは勘弁してくださいな」
難しい話である。でもそもそもこの物件が売りに出ている、ということを知らねば、買い手の幅が広がらないではないか。少なくとも不動産会社には売るということを言わないとそもそも話が進まない。私も彼にかなり抵抗はしたものの、言うことを聞かない。そんなこともあって、こういう妥協案を出した。
「わかりました。商工会議所への相談ですので担当の栗沢君、そして地元で古くから営んでいる石野不動産さんだけにお話しをしましょう。ここの不動産屋なら私も前職時代にお世話になったこともあるので仕事の信用も置けますし、また独自の情報も広くお持ちであると思います。またそういったことも含めて秘密裏にその情報をうまく使い売却活動をしていただけると思います。ただ赤元さんが病気になっていることは秘密厳守で、将来のこと、相続のことを考え早い目に手を打って置きたいための売却、とだけ伝えましょう」
「先生、そんなら大丈夫だと思いますわ。ありがとう、これで冥途に行ける準備ができますわ、ありがとう」
といいつつ、いきなり私の手を掴んだ、と思ったら握手だった。節くれ立った手の甲が職人としての歴史を如実に表していた。
Ⅴ
赤元氏から奥さんへの自宅の名義変更はすんなりと進んでいった。奥さんが自宅をもらうことを、逆に恐縮がってはいたが、赤元氏が、俺からのお前に苦労を掛けた迷惑料や、と言いつつ名義変更の書類にサインをしている赤元夫婦は、まさにおしどり夫婦と言えるものであった。
一方、工場の売却については難航、というよりは音沙汰がない、というのがぴったりとした表現であった。そもそも工場が売りに出ていることを広く知らしめるな、という条件下、これはそもそも売れないのではないか、と思いつつあったところだった。あと一週間なにも引き合いがなければ、赤元氏をもう一度説得せねばならない、と考えていた。
ところが、である。
石野不動産から私宛の電話で、長らく当地を訳あって離れていた大阪の技術者が、七十歳を前にして故郷に帰って後継ぎの息子ととともに事業をやりたいので、土地を探している、出来れば建物として工場も建っていてもらえればなおいい、という話がある、とのことだった。
「前園さん、でもちょっと妙なところがありましてね。この話は私の古くからの付き合いのある不動産屋からの話なんですけどね、なんでも具体的に売買の話が進むまで、契約を巻くまでは売主である赤元さんに身元を知られたくない、その代わりあの場所であれば絶対に買わせていただきたい、っておっしゃっているらしくて。しばらくは不動産屋同士での話になりそうなんです、それでもいいですか」
「はい、よろしくお願いします。買ってくれるというだけでも私はありがたいと思っておりますので。赤元さんにもそう私からも申し上げておきます。しかしその『絶対に』というところはどういうことでしょう。買主さんになにか事情があるのでしょうか」
「詳しくは分からないのですが、相手の不動産屋が言うところには、市内で土地を探している、という申し出があって、赤元さんの物件の詳細を見せたところ、先方さんは明らかに動揺したようで、そこから、身元は明かすな、絶対に買いたい、との話になったようなんです。でも、この物件を買うための銀行の融資もすんなりつくような感じだとのことなので、善は急げ、で私から今から赤元さんに電話しておきましょうか」
「はい、よろしくお願いします」
赤元氏との約束もあり、なかなか急いでほしいとは、こちらからは言いづらいところ、石野不動産から、善は急げという言葉が出たことに、この売買は旨く行くのではないか、と自然にそう思えた。
ただ、一体何でもそんないい話があるのだろうか。私は一人で少し考えてみた。買主には怪しいところはあるものの、この契約が成立して赤元氏には何のリスクもないように思われた。むしろ、絶対に、と言っているところを見ると、この話は乗るべきだろう、そう思い、石野不動産との電話が終わったころを見計らって、私からも赤元氏に電話をした。
彼は二つ返事でよろしく頼んます、と答えてくれた。ただそのあとでこんなことを言った。
「先生、石野不動産さんには言わなかったけれどもですな、わし昨日から入院しておりまして。いや気は元気なんですが、どうも身体が言うこと聞かんようになってきた感じがするんですわ。まだまだ元気でおるつもりでいるのですが、なるべく早く不動産の方、よろしくお願いしますわ」
私は一瞬言葉を失った。それこそ残された時間は本当に短いのだ、ということを悟った。それから赤元氏に何を言ったかは覚えてはいない、ただ、気を確かに、と言ったような気がするが、それは実際には自分に掛けた言葉でもある。そんなことを後から思った。
そのまま気の利いた言葉をかけることも出来ずに通話を終えた。
石野不動産たちの尽力で意外と早く話はまとまった。売買価格は二千五百万円。本来であればあのガラクタみたいな工具類、機械類の片付け費用を見越して売買価格は下げられるのが常であるが、買主は、ろくに価格交渉もせず、出来る限り再利用するのそれでいい、との話をしてきたらしい。
そのことを報告しに、石野不動産と私は連れ立って、赤元氏の病床へ行った。彼は二つ返事で了承をした。これで嫁と娘に借金を返済したうえに、わずかだが財産を残してあげられる・・・わしの生き方は間違いではなかったんだな、そう涙ながらに語る彼に対し、我々は言葉が出なかった。
正式な契約は、赤元氏の一時退院の日で、売買に適した日を選んで設定された。その日には石野不動産に買主も出てきて挨拶をしたい、との話であった。
私も部外者ながら、赤元氏に請われて付き添いで行くことになった。
「身分もいまだに明かさないようなヤツですやろ、何か変な言動があったら、先生、お願いしますわ」
私は武道の心得もないから変なことになった場合、力で解決できるわけがない。でも、、今更いちゃもんをつけたりするようなことにはならないとの確信もあった。
が、その予想は意外な形で裏切られることになる。
Ⅵ
契約の会合は十月の秋晴れの日だった。街中にある石野不動産は老舗だけあって建物も年季が入っている。商工会議所から歩いて三分もかからぬところにあり、待ち合わせは十時だったから、ちょっとだけ仕事を終えてから行くことにした。
少し早い目に私は到着したが、既に石野不動産に買主は来ていた。それほど広くはない応接室に、がっちりとした白髪の初老の男と、その息子と思しきこれも色の黒い体格のよい四十からみの壮年の男がいた。二人とも薄青色の作業服を着ており、胸には「本橋工業」とのオレンジ色のやや色あせた刺繍があった。隣にいるスーツの男は買主側の不動産屋であろう。
私はその三人とあいさつの後、しばし雑談をした。若いころ独り立ちしたくて当地から大阪へ独立開業し、そこから色々考えるところがあって、還暦を越えたころから故郷で仕事がしたいと強く思うようになったこと、息子も跡を継いでくれる、という話であったので、親子で話し合って、今回の物件を見つけ、今日の日に至った、との話だった。が、初老の男は何かしら落ち着かない様子だったのが、少し私には気になった。
しばらくして、赤元氏が奥さんと一緒に現れた。買主を見るなり、叫ぶように言った。
「本橋やないか!」
初老の買主の男は、サッと立ち上がり深々と頭を下げた。続けて息子も同じようにする。
「赤元さん、奥さん、私は昔、謝っても謝り切れない、申し訳ないことをしでかしました、お詫びの仕様もありません・・・」
赤元氏は黙っていた。奥さんも突っ立ったまま、目から涙を流れるままにしている。本橋氏も息子も身動きだにしない・・・
私や石野不動産は何が起こっているのか分からない。相手の不動産屋はある程度事情は飲み込めているようで静かに座っている。
最初に口火を切ったのは赤元氏だった。
「そんな、謝ってもらおうなんてちっとも思ってない、昔のことや。終わったことや。まあ座れや」
おとなしく親子は椅子に腰を掛ける。赤元氏夫妻も彼らと向かい合わせのソファーに座り、しばらく沈黙が流れていた。
しばしの間の後、今度は本橋氏がぽつりぽつりと話し始める。
「赤元さんにお借りしたお金ですが、今回の不動産とは別で絶対にお返ししたいと思っています」
私もその言葉で事態が飲み込めた。そう、本橋氏は赤元氏からお金を借りてそのままいなくなった張本人なのだ。それがために赤元氏は今でも借金を背負っており、長らくの懸念事項となっているのである。
本橋氏は続けて言う。
七十歳までに赤元氏に直接会って詫びを入れ、借りた金を全額返したいと思っていた。 ただ、そこまでの金額を作るのには長い道のりが必要だったし、今も完全に返せるだけの蓄財が出来たわけではない。事業を立て直しするの十五年、実質的に息子に事業を引継ぐのに五年が、併せて二十年もの年月が経過した。思いのほか時間が経過していく中で、いつか故郷に帰って何とかしようと思っていたところに、赤元機電工作所が売りに出されていることを知った。そして悟った、赤元先輩ももう事業を畳もうとしているのだと。本橋氏は、技術に対する哲学と素晴らしいアイデアを惜しみなく教えてくれた赤元先輩が作ったこの工場が、もしかしたら自分の借りた金のせいで無くなってしまうことにどうしようもない後悔の念で苛まされ、そしてこういう結論に至った。
ものすごく図々しい考えかもしれないが、自分が継ぐことが、自分が死んでも自分の息子が継ぐのが、使命だと思った、と本橋氏は言う。彼の息子にも話したところ、大いになじられ、かつ大いに賛成してもらった。親ばかだと思うが出来た息子だと思う。ここまで来たのも赤元先輩のおかげだ、ただ何も返せていないのは、私の本当に不徳の致すところだ。今回の工場を購入するにも借入がほとんどであり、借りっぱなしになっているお金を返済する貯蓄はない。しかし、あの工場が売りに出ていることは、赤元氏が仕事を辞めることなのだろうから、買い取った後赤元氏の意思を引き継いで、必ずこの事業を伸ばす、そして、何年かかっても赤元先輩に耳をそろえて返したい。しかし、買主として名を明かせば会ってもらえないかもしれない、そこのところも気が小さい自分が悲しくなるが、本当にそれも含めて許してほしい・・・何としてもお会いしたかったんです・・・。
狭い応接室に静かな重い空気が流れる。
「本橋よ。わしも人間だから一時期はお前のことを恨んだこともある」
再度の沈黙を破って赤元氏が言う。
「ただな、お前が逃げたということは、俺よりも苦労をしてやむにやまれぬ事態だった、ということは分かるようになった。お前に逃げられる、ということはわしの方にも、どこかで不徳の致すところがあったんだろう、と思えるまでになった。技術屋の先輩としてだけではなく、むしろ自営業の先輩としてもっと説教を垂れるべきところ、金を簡単に貸してしまったことも原因かもしれん。確かにわしは借金を背負ったが、儲けは少ないながらも地元の人に愛されながら、やりがいを持って仕事をやってこれた。このやってきた仕事の最後に借金も今回の売買でチャラになる。さらに、嫁や娘にそれなりのお金も残せてやるようになったのは、本橋、お前が工場を買うてくれるからやないか」
「それだけでは足りません。何年かかってでもお返し致します」
「いや、借金はチャラや、のう?」
と隣にいる奥さんの方を向く。奥さんは微笑みながら、うなずいている。
「それよりもな、本橋、わしはなあ、医者から余命宣告もされててな、お前に借金を返してもらっても、その金を使う時間もあらへんのや」
本橋氏はハッと目を見開いたと思うと同時に、男泣きに泣き崩れた、ごめんなさい、申し訳ない、と言いながら・・・。
その様子を眺めながら、赤元氏は続ける。
「今思ったんやけどな、お前のほうが今は経営者としては、わしより上や。わしが出来んかった事業承継も立派な息子さんが継いでくれる、よっぽど前々から準備しておったんやろうなあ。その点わしは跡継ぎもおらへんのに、自分自身の能力を恃み、ろくに自分の技術の伝承もしなかった。そして病気になって初めて、こうして慌てて工場を売りに出さなあかんようになってしまった。でもな、わしが作った工場を、人生の最後で、因縁のあった男に、そしてその息子さんにバトンタッチできるのは、幸せやで」
そういいつつ、赤元氏は本橋氏の息子のほうを向き、
「わしらロートルはもう引退せなあかん。これからはあんたがこの工場をうまく引き継いでってや」
まだうつむく父親の横で、若き経営者は目を真っ赤にしながらも、力強く首を縦に振った。
Ⅶ
その後、売買契約締結も、後日の売買決済もスムーズに行われ、赤元氏は借金の返済と相応の財産を残したことを見届けた。
それから六か月後、医師の余命宣告通り赤元氏は逝った。
私は奥さんから強く頼まれ、通夜から告別式、その後の法事まで一通り取り仕切り、この間、初盆の法事もつつがなく執り行わせてもらった。
本橋親子は買い取った工場の整理と簡単な改築を終えて、ところどころに古い部分が残る建物で、事業の運営をしている。受注は好調のようだ。
その工場の入口には、本橋親子の手で作られたプレートが掲げられている。
『この工場は創意工夫と技術を何より尊んだ赤元源蔵により創建された』

書いたあとで
書いてから一年余りが経った今、改めて今読み直してみた。なんか自分て損な役割してるよなーとか、自分の作品でなく読めた。ちょっとだけ泣けた、まあ色々思い入れがある作品だからさあ。
なぜ今、ブログに載せたのか。前々からこれはやりたいと思ってた。前回受賞のやつもそうしてたし、まあ一冊の本にはなっているけれど、四日市市立図書館に残っているのでそこまで行かねば見れない、とは悲しいなとは思えたので、ちょっと日の目を浴びさせてみました。
書いた当時と、今の自分の距離はうーん、いまも同じことやってるなあというのが正直な感想。まあ泥臭い後処理をしてますわ。
で、やっぱり、というかだから、というか現実は物語のようには整わなかったんですわ。実際。そのまま工場は塩漬けになったまま、だったかな? 俺だって現実ばかり見たくないときもある、そうしてこんな物語を書くことくらいは許されるだろう、と勝手に感じて、気が向けば物語を今でも書いたりしてます。
それでも、この作品を残す理由:うーん、これはさ、未練だよね、きっと。
読者への一言:まあ読んでやってくださいな。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。








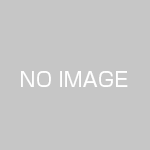
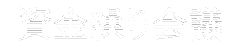
この記事へのコメントはありません。